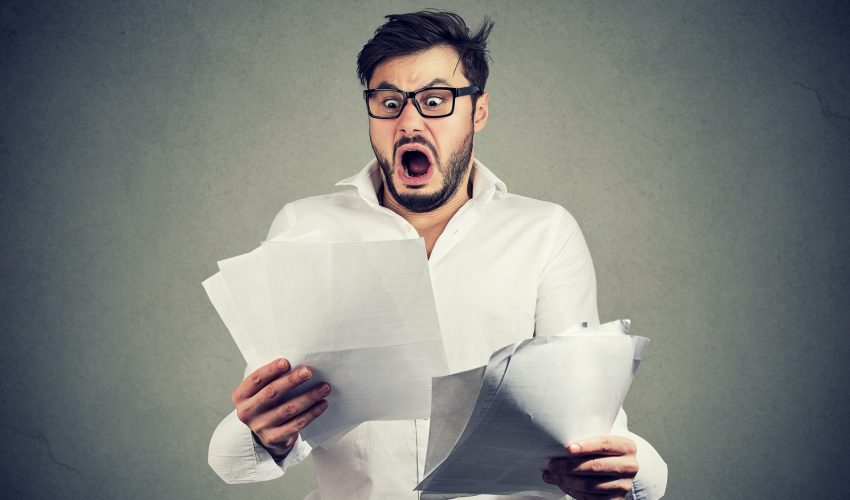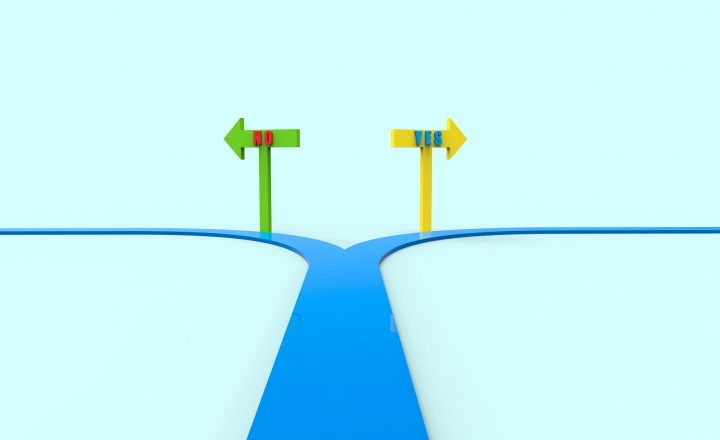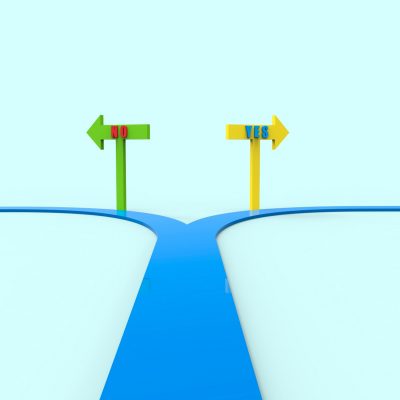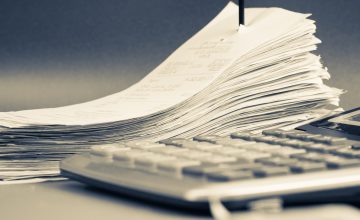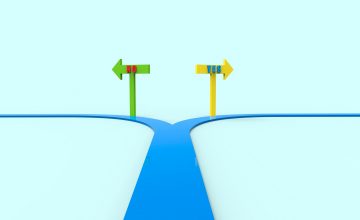個人事業主と法人では支払う税金も税率も異なりますが、個人事業の方が税金が高いので法人成りの方がいいという見方もあります。実際には個人事業と法人どちらが節税できるのでしょうか?この記事では、個人事業の税率と法人の税率を比較してご説明します。
1.個人事業主と法人では納める税金の種類が違う

Taxes Concept. Word on Folder Register of Card Index. Selective Focus.
個人事業主が納める主な税金は4種類あり、
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
となっています。
それに対し法人は、基本的に
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 固定資産税
- 地方法人特別税(令和元年9月30日に廃止されます)
- 特別法人事業税(令和元年10月1日より開始されます)
の6種類の税金を支払わなければいけません。個人事業主より法人の方が税金の種類は多いんですね。
個人事業主の方が税金の種類が少ないのになぜ法人より税金が高いと言われるのでしょうか?それは、個人事業主の所得が多くなると法人に比べ税率が割高になるからです。個人事業主が納める所得税と法人が納める法人税を例に税率を比較してみましょう。
まず、所得税とは個人事業主の1年間の所得に対して課される税金です。所得税の税率は所得金額(収入から必要経費を差し引いた額)が多ければ多いほど高くなっていきます。この仕組みを「累進課税」と言います。例えば、所得が500万円なら税率は20%ですが、所得が4,000万円を超えると税率も45%になり、所得の半分近くが所得税として徴収されることになります。
法人が納める法人税とは、所得税のように収入から必要経費を引いた1年間の所得に対して課される税金ですが、所得税との大きな違いは累進課税ではなく税率が一律となっていることと、税率の上限が低く設定されている点です。
所得税は所得金額によって税率が細かく設定されているのに対し、法人税は所得金額が800万円以下の部分には税率が15%、800万円を超える部分は税率が23.2%となっています。
法人税と所得税の税率を比較していくと、所得金額が少ないうちは所得税の税率の方が低いですが、ある程度所得が増えてくると法人の方が節税できるでしょう。税率の上限も所得税は最大税率45%だったのに対し、法人税は最大税率23.9%と法人の方が低く設定されています。
2 .個人事業主の税金が高いと言われる理由

個人事業主の税金が高いと言われる理由は他にもあります。例えば、法人になれば給与所得控除を利用できるようになります。給与所得控除とは給与に対して一定額の税金の負担を減らしてくれる仕組みです。
例えば、サラリーマンなら会社が計算して収入の一部の税金が給与所得控除によって免除されています。個人事業主は自分に給与を支払う事はできないため給与所得控除は利用できませんが、法人なら法人から社長に給与が支払われるため、給与所得控除を自分(社長)も利用できます。
例で考えてみましょう。個人事業主の場合1,000万円の売り上げと400万円の経費がかかったとします。所得金額の600万円から所得税を計算しますので約70万円が所得税となります。法人の場合、同じように600万円を会社から社長に給与として払うことができ、給与控除を計算すると約174万円になります。
もともと600万円の給与から174万円を引いた426万円が所得金額となります。所得金額426万円から所得税を計算すると約35万円となります。これだけでも35万円の節税になってますが、住民税や個人事業税など細かく計算していくと法人の方が節税できる事がわかってきます。
さらに、法人であれば家族に役員報酬を支払う事ができるようになります。
つまり社長が1人で全額を受け取るのではなく妻や子供に役員報酬を支払う事で一人当たりの所得を分散できるのです。所得税は所得金額によって変わってきますので一人当たりの所得を減らせば家族全体の収入は変わらずに税金を抑える事ができます。
他にも、個人事業であれば仕事をやめたとしても退職金を受け取ることはできませんが、法人であれば会社から自分や家族従業員に退職金を支給できるようになります。退職金は退職所得になり退職所得控除が適用されるのでかなり節税になります。また、退職金は分離課税になり税金は給与所得と分けて計算されるため低い税率に抑える事ができます。
3 .まとめ
個人事業の方が法人より税金が高いと言われる理由をご紹介しました。確かに法人の方が税金の種類は多いにも関わらず場合によっては個人事業主よりも節税できます。
特に所得がある程度多くなると法人税に比べ累進課税の所得税の方が税率が高くなりますし、給与所得控除など個人事業主では利用できないものもあります。しかし、全ての個人事業主が法人化した方が節税できるというわけではありませんので、まずは現在の所得から細かくシミュレーションしてみましょう。